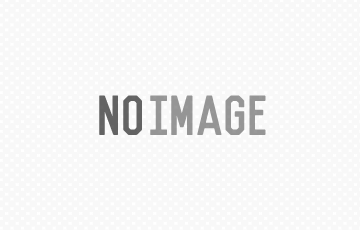論理的・感情
岡田斗司夫の動画見てて、「チ。」の作者の「ようこそfactへ」みたいな、論理的だけど陰謀論にハマって行く人を描いた漫画を解説してたけど・・
魚豊『ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ』が面白い!幻冬舎の箕輪氏も絶賛 チ。の作者【岡田斗司夫のエンタメ話】切り抜き動画
論理って、自分の納得感ベースで、論理的に組み立て行くけど、自分の枠内から出られないみたいな。
結局外の人から見たら論理的じゃないみたいな状態になるけど、
学問の世界とかでも、男の納得感ベースで組み立られてることが多いから、女性視点で見ると、「それどうなん?」ってことが意外とあったりする。
トルストイの「アンナカレーニナ」でもそんなこと表現したいんだろうなってのが、うかがえるんだけど。
で、話はそことちょっとズレるんだけど、
男の論理的な判断の時に使う、「納得感」みたいなものと、女性が判断する時に使う、自分の「感情」がどう感じるか?
みたいなものは、もしかしたら、同じ位置付けなのかもなって気がしてきた。
で、俺って社会で言う「論理的」って感覚を27ぐらいで、気づいたんだけど←おそ
それと同じで、女性の「感情」って感覚も、後天的に身につけられるのかもしれない。
そしたら、女性にモテる度もっと上がるかもな。
みたいなことを思いました。
そういえば、カントの本に、「判断力批判」みたいな本あったな。
カントとかが、そこらへん考えてるのかもな。
カントの「純粋理性批判」はいつかは読みたいなと思ってたけど、他にも色々読んでみたい。
判断する時に使うのが、「納得感」「感情」とか色々分析してるだろうな。カントは。
で、男女によって、その使う時の比重が違うみたいな。
雑記:本の難易度
難易度でいえば、トルストイの「戦争と平和」>「アンナカレーニナ」だと勝手にイメージしてたけど、
「アンナカレーニナ」>「戦争と平和」かもしれん。って思い始めまた。(「戦争と平和」読んでないから分からんけど。)
抽象度的に、トルストイが40代で書いた「アンナカレーニナ」の方が、30代で書いた「戦争と平和」よりも高いんじゃないかなって気がする。
「アンナカレーニナ」ってカタカナのタイトルだとか、題材が浮気だから騙されてたけど。
物理学とか、哲学的な分野でも、
30代のマルクスガブリエルの「世界は存在しない」よりも、60代のカルロ・ロヴェッリが書いた「時間は存在しない」の方が、文章平易だけど、抽象度高いなって思ったし。(まあ「世界は存在しない」も読んでないんですけどね。パラパラ見た感じ。)
文章自体は平易なんだけど、内容はむずいみたいなことが結構ある。
それと同じことがカテゴリーでも起きて、文学って分野も、エンタメみたいなイメージを持ってたから簡単だと思ってたけど、意外と情報量濃いというか、抽象度高いなって思いましたし。アンナカレーニナ読んでて。
これらのまた発展系としては、男が読む「源氏物語」は、めちゃくちゃ難易度高いなって気がしますねー。
女性視点で人が動くから、めっちゃ難しいなって。
男目線だと、
- 貴族社会の人間の動き、察し合い的な人間の動き方とかも知ってないといけないし、
- 女性視点も掴んでないといけないし
みたいな。
女性目線だと、本能的に察する力のレベルは高いし、女性視点もできるしだから、源氏物語の理解度が高かったりするみたいな。
事実、よく分からん男の学者が、源氏物語を解説とかしてるの見ると、的外れも良いところなことが多々ありますし。そこらへんの女性に読んでもらった方が、源氏物語を理解してくれるみたいな。
男が源氏物語読むのは、
普通に、マルクスとかみたいな、かっちりした本を、読むぐらいの難易度と、準備が必要って捉えて良いのかもなって気がしますねー
まあマルクス読んだことないですけど。
そして、わい、そろそろ源氏物語読む段階に入りつつあるな。って感覚があるので、鼻高々なんにょ